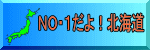
| 1位 | 釧網線 JR北海道 釧路〜網走169・1キロ |
流氷の眺められる網走-知床斜里・釧路湿原とタンチョウヅルの見える 標茶-東釧路がポイント。 |
| 2位 | 五能線 JR東日本 東能代〜川部147・2キロ |
青森・秋田両県の日本海側をへばりつくように走る。岩木山のただずまいも印象的。車窓から世界遺産の白神山地が見える。不老不死の最寄り駅は艫作(へなし) |
| 3位 | 只見線 JR東日本 会津若松〜小出135・2キロ |
只見川の渓谷美に感動・鉄橋が多い。 全線乗車に4時間強・「真冬の雪の深さを実感できる。 |
| 4位 | 津軽鉄道 私鉄 津軽五所川原〜津軽中里20・7キロ |
金木町出身の作家、太宰治にちなんだ「走れメロス号」を運転。 夏には風鈴列車を走らせる |
| 5位 | 宗谷本線 JR東日本 旭川〜稚内259・4キロ |
サロベツ原野の寂寥感に味わい。稚内は国内最北端の駅。 宗谷岬には同駅から50分。 |
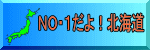
| 星座名 | 順位 | 季節 | 明るい星の名前 | 意味 | 語源 | 距離(光年 | 星の色 |
| おおいぬ | 1 | 冬 | シリウス | 焼き焦がすもの | ギリシャ語 | 8.6 | 青白 |
| りゅうこつ | 2 | 南天 | カノープス | ギリシャ神話のメネラオス王の 水先案内人の名前 |
250 | 青白 | |
| ケンタウルス座α星 | 3 | 4・3 | 黄色 | ||||
| うしかい | 4 | 春 | アークトゥルス | 熊の番人 | ギリシャ語 | 37 | 橙 |
| こと | 5 | 夏 | ベガ | 落ちるわし | アラビア語 | 25 | 青白 |
| オリオン | 6 | 冬 | リゲル | 巨人の足 | アラビア語 | 800 | 青白 |
| ぎょしゃ | 7 | 冬 | カペラ | かわいい雌やぎ | ラテン語 | 42 | 黄色 |
| こいぬ | 8 | 冬 | プロキオン | 犬の前に | ギリシャ語 | 11.5 | 白 |
| エリダヌス座α星 | 9 | アケルナイ | 80 | 青白 | |||
| わし | 10 | 夏 | アルタイル | 飛ぶわし | アラビア語 | 16.8 | 青白 |
| おうし | 11 | 冬 | アルデバラン | 後につづくもの | アラビア語 | 64 | 橙 |
| オリオン | 12 | 冬 | ベテルギウス | わきの下 | アラビア語 | 450 | 赤 |
| さそり | 13 | 夏 | アンタレス | 火星のライバル | ギリシャ語 | 550 | 赤 |
| おとめ | 14 | 春 | スピカ | 麦の穂 | ラテン語 | 270 | 青白 |
| ふたご | 15 | 冬 | ポルックス | レダの双子の息子の弟の名前 | 32 | 橙 | |
| みなみのうお | 16 | 秋 | フォーマルハウト | 南のうおの口 | アラビア語 | 25 | 青白 |
| はくちょう | 17 | 春 | デネブ | 尾 | アラビア語 | 2000 | 青白 |
| しし | 18 | 春 | レグルス | 小さな王 | ラテン語 | 78 | 青白 |
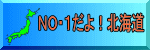
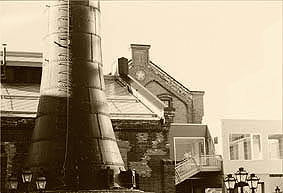 かつてのビール工場のシンボル、煙突
|
 千歳市の支笏湖ユースホステル旧館は、建築家田上義也氏の設計で、昭和35年に建設された日本第1号のユースホステル。 雪国的造型を意識した「三角屋根」と採光のためのガラスが多用されている。 |
支笏湖から見た樽前山 緑豊かな原生林に囲まれた、周囲約42kmの大カルデラ湖。約4万年前の激しい噴火活動によってでき、最大水深は約360mと日本で2番目。透明度が高く、水質では日本一に輝いた実績を持つ。周囲は恵庭岳[えにわだけ]、風不死岳[ふっぷしだけ]、樽前山などに取り囲まれ、支笏湖観光遊覧船に乗船すれば湖上から景観を満喫できる。支笏湖とその南西に位置する洞爺湖一帯は支笏洞爺国立公園に指定。 |
| 釧路湿原は、総面積約180km2にもおよび、国内の湿原面積の約6割を占めている。湿原全体に生育するヨシと散在するハンノキ林、 蛇行する河川などから構成される湿原は動植物の宝庫。 日本最大級の淡水魚イトウが生息し、 国の特別天然記念物のタンチョウが飛ぶ姿や、人里近くまでエサを求めてくる姿を見ることができる。 |
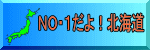
| 高速道路(帯広・広尾自動車道)ができることで、エゾモモンガが棲家としている林が分断され、生態系が乱されるのを防ぐためのもの。 モモンガの橋は正式には「道路横断構造物」というお堅い名称。 |
| 搾ったままの牛乳には雑菌が入っていることから、牛乳として販売するには殺菌するのが通常である。ところが十勝の中札内村にある中札内村レディースファームでは、日々の徹底した飼育管理によりストレスのない乳牛から、有害雑菌のいない原乳を搾ることができた。 そして平成14年5月、無殺菌牛乳「想いやり牛乳」の製品化に成功。 札幌や旭川、釧路などで販売されている。 「国内では唯一うちだけ。匂いがなく、口当たりもいい。牛乳の嫌いな人でも飲めますよ」と社長さんの話 |
ネットで調べて売ってるお店を調べて 買ってきました。 これ一本で210円。 健康に良いものは高い? |
 |
室蘭市内に数多くある焼き鳥屋の肉には、豚肉が使われることが多い。 その原因は、江戸時代までさかのぼる。当時は庶民が自由に肉を口にすることは禁止されており、特権階級にのみ許されたものだったが、焼き鳥の調理法は確立されていた。 明治以降、庶民にも肉を食べることが許され、 野鳥をはじめ豚の臓物を串焼きにしたものを総称して 「焼き鳥」と呼ぶようになった。その名残から、豚を使っていても焼き鳥と呼ばれている |
火口底のガスが湧きだし80度から100度の熱泥が噴き上げています。付近の原始林散策路は強烈な硫黄の臭い。 冬は立ち上がる蒸気が凍り、美しい樹氷が見られます。 |
 |
「坊ちゃん」や「吾輩は猫である」などの作品で知られる文豪夏目漱石が20年以上もの間、 岩内町に戸籍を移していたというのは真実。戸籍を移した 明治25年当時は北海道は開拓地としてまだ徴兵制が適用されておらず、 漱石の父が家名を存続させようと徴兵逃れの為に戸籍を移したといわれている。 現在はその戸籍があった場所に記念碑が建てられている |
 |
最も気温が低くなる2月頃、四角形や六角形、ワイングラス型の太陽が昇ることがある。もちろん太陽が本当に変形してしまうのではなく、いわゆる蜃気楼現象のひとつ。気温がマイナス20℃以下に下がり、その上空に暖かい空気があることが必須条件。自然現象なので、条件を満たしていても必ず見えるわけではない。年に数回しか見ることができないので、もし見ることができたなら、本当に幸運である。 ●オホーツク・ガリンコタワー 01582(3)1100 写真を無断借用させてもらいました |
 |
寒さが厳しい街として知られる名寄市では、 1月下旬から3月上旬のマイナス20℃の 厳寒の時期になると、氷の結晶が光に反応して柱のように立ちのぼる不思議な現象が 起こることがある。名寄の観光協会によると「しばれた日で、雪が降らず天気がよく太陽が出ていること」が条件という。 名寄ピヤシリスキー場や隣のピヤシリ山などで多く見られ、朝陽か夕陽、あるいは電柱の光(ライトピラーと呼ぶ)でも発生するという。 ちなみに、「サンピラー娘」というピクルスが地元では売られている。 ●まちづくり協会 01654(9)6711 (名寄市HPより写真を無断借用しました。平成10年1月ピヤシリスキー場) |
 |
十勝の鹿追町にある然別湖は真冬にはマイナス30℃を下回るという 北海道でも最も寒い地域にある湖。 1月下旬になると湖に張った氷は約1mにもなる。 その凍結した湖の上に「然別湖コタン」と呼ばれる 冬だけの村ができるのだ。 この村はすべてが雪と氷でできている。イグルーと呼ばれる住居やカクテルが楽しめるアイスバー、 そして温泉露天風呂まで出現する。 この温泉は湖畔の然別温泉から引かれたもので、湯船から湖上を見渡す360度の景観はここだけの爽快さ。 服を脱ぐ脱衣所まで氷で作られているという徹底ぶりだ。 ●然別湖ネイチャーセンター 01566(9)8181 |
| 由仁町を流れる一級河川石狩川水系「ヤリキレナイ川」はオモシロ地名として知られている。 この名前はアイヌ語の「ヤンケナイ川」「イヤルキナイ川」がなまったものというのが定説で「入植した開拓民が洪水ばかりで『やりきれなくなった』ため」というのは俗説とされてきた。 しかし、語源的に分析すると「ヤラ・キロロ・ナイ(破れる・力の・川)」となり、やはり昔から大雨でよく氾濫していたんだろうと思われる。 ちなみに共和町には底はあるのに「宿内川(そこない)」、雨竜町には「面白内川(オモシロナイ)」 というオモシロ地名がある。 |